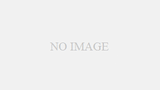机に向かうのが億劫…
社会人やっていると(主語デカ)、仕事から帰宅して、シャワー浴びて、ご飯食べて、、の時点で気力が湧かなくなる。というか休日もPCに向かうまでにものすごくエネルギーが要る。やらなきゃいけないと思うけど、体が動かない。机に向かったほうがいいのは分かるし勉強することで今後の人生も…とかも理解できる。けどどうも報酬が年単位で先過ぎてやる気が…
copilotに聞いてみた
🧠 原因:脳科学的なモチベーション低下のメカニズム
1. ドーパミン不足
- ドーパミンは「やる気」や「快感」に関わる神経伝達物質。
- 目標が曖昧だったり、達成感が得られないと分泌が減る。
2. 報酬予測の不一致
- 脳は「これをやれば報酬が得られる」と予測して行動する。
- 勉強の成果が見えにくいと、報酬予測が成立せず、やる気が出ない。
3. 扁桃体の過活動(ストレス)
- ストレスや不安が強いと、扁桃体が活性化して前頭前野(論理的思考や計画を司る部分)の働きを妨げる。
- 「やらなきゃ」と思うほど逆に動けなくなる。
🔧 対策:脳を味方につけるモチベーション戦略
1. 小さな報酬を設定する
- 例:「25分集中したら5分休憩+好きな動画1本」など。
- ドーパミンを意図的に分泌させることで、脳が「やる価値あり」と判断する。
2. 目標を“見える化”する
- カレンダーやToDoリストに「達成済み」を記録すると、報酬系が活性化。
- 脳は「進捗が見える」ことでやる気を維持しやすい。
3. 勉強の意味づけを再定義する
- 「この勉強が将来の○○につながる」と意味を持たせると、前頭前野が活性化。
- 抽象的な目的より、具体的な未来像が効果的。
4. 環境を変える
- 例:朝のカフェで勉強する、アプリで記録をつけるなど。
- 場所・時間・ツールを変えることで脳が「新しい刺激」と認識し、活性化する。
結局①
「勉強したらマンガ読んでいい」「お菓子」「動画」類なんて別に勉強しなくても読めるし食べるし見るし。そこに強制力が無いから残念ながら機能しない。目標を見える化しても、残念ながら強く願ったり心の底から湧き出るような渇望でもないのでモチベにはなりにくい。カフェは面倒…
イヤイヤ三昧だけど、一点アプリでの勉強記録をつけるのは良いと思った。そもそも中高と授業以外で進んで勉強することがなかった。通信制の大学を選んだのも自分から勉強するという体験をしたかったからというのも理由のひとつ(その癖やらないけど)。だから大学授業を受けている時間や課題をこなしている時間を計測、記録とればその実績がモチベにつながるのではと思った。夏休みのラジオ体操カレンダー的な。
結局② -copilotで勉強記録カレンダーを作った-
ただ記録するにしても勉強する為にスマホアプリを起動するのは面倒。面倒な勉強をするために面倒を増やすのは本末転倒。なのでwebアプリにした。(ほかの人からしたらどっちもどっちだけど、自分はwebの方が仕事関数が低い)①記録アプリを開始するために、カレンダーを埋めるために机に向かわないといけない、②その後勉強時間を見返せて自信になる。いいアプリ(まだ対して使用していないけど。)
ちなみにプログラムはたいして組めないし面倒だからcopilot先生に全部書いてもらった。意外とやってくれる。本業の方でもそこそこマクロ書いてくれるし。てか情報科に入学したのにプログラム面倒て…
以下にカレンダーのリンクを張っておくので良ければ使用してみてください。世の中にはこれの10^4倍良いアプリはあるだろうけど、pc使いながら勉強する人にはちょうどいいかも。
勉強時間はユーザーPCのキャッシュに保存するようになっている(適宜CSV出力もできる)し、変にプログラムをダウンロードする必要もないので気兼ねなく安全に使用できるはず。
勉強記録カレンダー